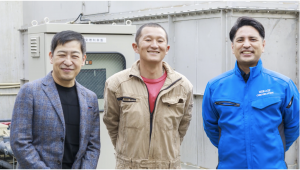廃菌床を“捨てる”から“活かす”へ。 地域循環を支える堆肥化
H社様
長野県中野市でえのき茸を生産するH社様では、廃菌床の堆肥化に早くから取り組まれてきました。
その中で課題だった、発酵の安定化を目指して導入されたのが「イージージェット」です。
現場での試行錯誤や導入後の変化についてお話を伺いました。
キノコ栽培の“スタート地点”と廃菌床の悩み

長野県は国産エノキ生産量の60%を占めています。
そんな中で私たち(H社様)は、キノコ種菌をつくる「培養センター」を運営しています。毎日コンテナで運ばれてくる菌床を育て、市内のキノコ農家さんへ送り出す、いわばキノコ栽培の“スタート地点”のような役割です。
そんな私たちにとって、避けて通れないのが「廃菌床」の処理です。
菌の培養が終わった菌床は、廃棄物として出てきます。しかし、水分が多いため発酵も乾燥もうまく進まず、腐敗すると臭いが出ます。ブロワを使用しますが温度が上がらないので、処理にとても時間がかかるなど、正直なところ「どうにかならないか」と悩んでいました。
イージージェットとの出会いと試験導入
そんなとき、ミライエさんのイージージェットを知りました。
正直、最初は半信半疑でした。「送風だけで、そんなに温度が上がるのか?」と。でも、営業の方から「試験で確認してみませんか」と提案を受けて、思い切ってテストを実施することにしたんです。
結果は上々でした。
当時75日かかっていた堆肥化が、試験時には50日程度で完了し、現場での実感としても手応えがありました。高い圧力で少量の空気を均一に送る仕組みなんですが、それが効いて、発酵がすごく安定するようになりました。
本格的にイージージェットを導入して一番有難かったのは、臭気です。以前は施設に近づくと嫌な臭いがしていたんですが、今ではほとんど気にならなくなりました。地域の方と共存していくためには、臭いの問題は避けて通れませんから、これは本当に助かっています。
中野市の冬はマイナス10度まで下がりますが、発酵温度は60~70℃まで上がります。
ブロワと併用することで水分も25%以下まで落とせるようになり、堆肥販売先からの評判もいいです。今となっては欠かせない装置になっています。

左:ミライエ代表 島田、右:H社代表理事様
廃菌床が資源へ ― 循環の仕組みづくり
現在は、1日10トンほどの廃菌床を処理しています。近隣の牛ふんや剪定枝などと混合して堆肥化し、地元の農家さんや、遠いところだと京都の九条ネギ農家さんにもお配りしています。臭いも少なく、ふかふかで扱いやすい堆肥だと喜ばれます。
もともと廃棄物だったものが、地域で活用できる「資源」になる。まさに循環型の仕組みを少しずつ実現できている実感があります。
導入の決断と広がる未来へ

導入前は、不安もありました。
設備投資は決して小さくないし、なにより「ほんとに効果があるのか?」という気持ちはありました。でも、ミライエさんは、こちらの悩みや現場の実態にしっかり寄り添ってくれました。「まず試して、納得してから導入を考えましょう」と言ってもらえたことで、安心して一歩を踏み出すことができました。
私たちの会社は、持続可能な地域づくりに貢献したいという想いを持っています。
廃棄物を出して終わりではなく、自分たちが生み出したものには責任を持って向き合いたい。大量生産・大量廃棄ではなく、地域の中で出たものを、地域の中で活かしていく。今回の堆肥化の取り組みは、その大きな一歩だったと感じています。
また、この仕組みはキノコ業界全体にとっても希望になるのではないかと思っています。廃菌床の処理に悩んでいる事業者は全国にたくさんいます。イージージェットのような技術が広がれば、廃棄コストの削減だけでなく、農業と連携した資源循環の新しいモデルが各地で生まれるかもしれません。
「廃棄物」として焼却されていた菌床が、地域の農家さんに喜ばれる「堆肥」へと生まれ変わる。これこそが、私たちが目指したかった姿です。
お客様について

H社 様
長野県中野市でえのき茸を中心に生産しているH社様では、日々発生する大量の廃菌床を「資源」と捉え、堆肥化による再利用を推進されています。きっかけは、もともとバイオセンターとして始まった施設に資材メーカーが加わり、肥料化の実証を重ねたこと。現在では、年間約7,700トンの菌床を処理し、そのうち2,600トンあまりを製品化。農家や畜産農家への販売も行われています。








 Facebook
Facebook X
X Hatena
Hatena Poket
Poket